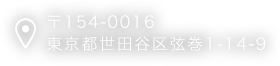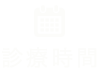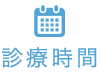大森塾を終えて
副院長の斉藤祐紀です。
2023年7月から月に一度月曜日の診療後に田町へ向かい、勉強会に参加しておりました。2年に及ぶ勉強会でしたが非常に有意義なものでした。講義をしていただくのが大阪SJCDの会長をされている大森有樹先生です。去年も何度か大阪へ実習セミナーの参加しておりましたが、その大森先生のセミナーでした。
大森先生にご指導いただきたく考えたきっかけは大手インプラントメーカーのストローマンで行われていた勉強会でした。それは大森先生が主催でその他複数の先生が講演されるものでしたがそこでの大森先生の講義で私は度肝を抜かれました。
臨床を行なっていて常日頃疑問に思っていたのが2点あります。
一つははぎしり、食いしばりによる歯や顎関節の不具合をその対処です。
いわゆる「力」の問題となりますが、これは大学教育ではあまり議題に上がらずもちろん国家試験などでもほぼ問われません。(顎関節症に関わるところだけは問われる)というのが「力」は虫歯や歯周病と比べて実験しづらい、客観的な評価をしにくいなどの性格から学問的には今のところしっかりとは体系化されていません。ただ現実に「力」の問題は存在し、それによって歯を悪くしている患者さんもいます。
力の問題で歯に起こるトラブルは
歯が欠ける、根っこが割れるといった破折
歯にヒビが入ってそこからの虫歯
歯に強い力がかかることによる歯槽骨の吸収(所見としては歯周病となる)
があり、力で直接的にトラブルが生じる場合もあれば、力によって間接的に虫歯や歯周病を引き起こしてしまうトラブルもあります。要は歯にヒビが入らなければ虫歯にならなかったし、歯に力がかからなければ骨吸収は生じず歯周病は悪化しなかっただろうということです。
虫歯や歯周病は生活習慣の改善である程度防ぐことは可能ですが力はコントロールが非常に厄介です。そのため一生懸命生活習慣を正している患者さんでも力により歯を悪くしているケースも目の当たりにしています。しかし多くの病院では結果としては虫歯、歯周病になってるからそれに対して気をつけましょうという話になってしまいます。要は力に対して対策できす、不幸にも歯が悪くなったら治療して対応するという形です。

ここが疑問の二つ目にもかかわるところですが、これは病態の原因の追求です。
私は歯科医師になって程なくしてから、「治療しても根本的な問題が解決しないと再発してしまう、あらかじめ何かできることはないのだろうか」と疑問を持ちながら過ごしておりました。しかし歯科界における勉強会では派手で特殊な技術、この「病気にはこの治療法!」みたいな局所的で、応用しづらいものも多くそもそもその病態をきちんと理解する前に派手な治し方を習得するというものが散見されます。これらは「病気になったらこのように治すのがエレガントである」というところであって、「そもそもなぜ病気になったのか、どうすれば防ぐことができたのか」の話ではありません。病気を治療して一度は修復できてもその病気の原因が取り除けないと再び病気になる可能性があります。治療法の追求は病気になってしまいそれに対する処置を行うことが前提です。
もちろん病気になってしまいそれが治療によりきれいに治ることは素晴らしいことですが、そもそも病気にならないようにする方が苦しみも少なく生活する上で快適ですよね。派手さはなく地味なところかもしれませんが病気を防ぐことはQOL(クオリティオブライフ)において最も優れることと思われます。
したがってもう病気を繰り返さないための原因追求、病気になる可能性の排除のためのリスク診断を重視する歯科臨床こそが本質ではないか、このようなことを私は臨床していてどうにかならないかと考えていました。そんな中で大森先生はその病態の原因論の追求と力に対する考察を非常に重視される先生で私が臨床をしていて抱いていた疑問と真っ直ぐに向き合っていらっしゃる先生でした。この先生の話をもっと聞きたいと思い、受講することにしました。ご多忙の中大阪から月に2回は東京にいらして講義されるほど歯科に対して非常に熱い想いを持った先生です。この2年間を経て私の歯科臨床は大きく変わりました。
大森先生は大阪では実習付きのプライベートセミナーも多数行っており、昨年は多数受講しました。そのブログの記載してますのでご参照ください。
なぜ仮歯は入れるのか
https://www.saito-dentaloffice.com/blog/634-2/
咬合、力、顎関節症への実践的アプローチコースを受けて
https://www.saito-dentaloffice.com/blog/咬合、力、顎関節顎関節症への実践的アプローチ/
大森塾では上記の病態の原因論や力のコントロールに関するだけでなく歯科における一通りの分野を学びます。したがって非常にバランスの良い知識が習得できます。例えば大学院へ進学することは一つの分野を極めその専門性を高めることができます。逆にいうとその分野以外ではその先生が個人的に修練しない限りそれほどの実力になりません。GP(一般歯科医)においてはその極まった専門性よりもバランスの良い実力と本当の難症例に関してはきちんと見極め、不要な手出しをせず専門家へ紹介する能力も問われます。
大学入試などで「たまたま得意な問題が出題されたからその大学に合格が出来た!」ではなくどんな問題が出ても合格点は通過できるような実力が必要と思われます。一つの得意な科目よりもどの科目もそれなりの点数を取る方が確実に合格しやすいですよね。私は浪人して東京医科歯科大学(現東京科学大学)へ入学したため講義を学びながら当時のことを思い出しました。
これらの講義と実習を重ねて実力を高めることにより来院される患者さんへの還元ができるようになったと自負しております。大森先生へは感謝してもしきれないほどのお世話になっており、今後も学ばせていただく機会を持ち続けたいと思います。