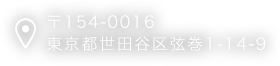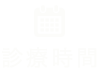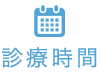マイクロスコープのさらなる可能性を求めて
副院長の斉藤祐紀です。
6/1は臨床応用顕微鏡歯科学会の第8回のハンズオンコースに参加しました。こちらの学会の会長秋山勝彦先生は「スリーステップ秋山メソッド」と呼ばれる歯科用手術顕微鏡の使用方法を開発されその有用性が日本のみならず世界的に高く評されており、またそれを用いることでこれまで不可能とされていた治療も成功されておりその面では唯一無二の歯科医師だと思われます。秋山先生の著書を拝読し当院も顕微鏡(マイクロスコープ)を導入しておりますが、それがまさに秋山先生が推奨されるモデルと同じであったため、「スリーステップ秋山メソッド」の入り口には立てると思い、受講を検討しました。先生の実習つきセミナーはすぐに満席になってしまうため受講する機会になかなか恵まれず今回ついに受講が叶いました。しかも場所がお茶の水という母校東京医科歯科大学(現、東京科学大学)の近くであり、3月まで勤務させていただいていた杏雲ビル歯科の付近でもありとても懐かしい場所で感慨深いものがありました。(思えば大学受験の浪人時代からお茶の水で過ごしていました)
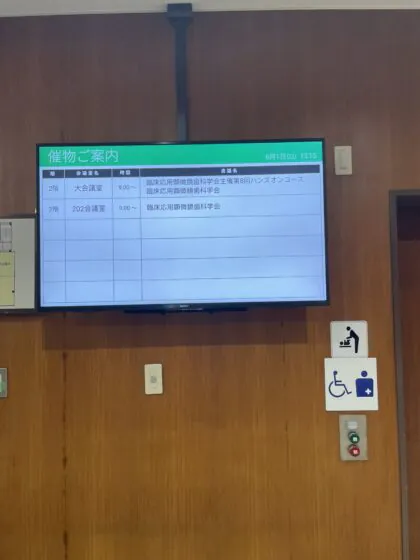
秋山先生が提唱される顕微鏡(マイクロスコープ)の使い方の重要なところとしては顕微鏡で直視をすることです。
歯科界では一般的にミラーテクニックと言われる、治療部位が見づらい、姿勢が取りづらいところではミラーを使って視認して治療を行います。しかし化粧や髪を整えるなど朝洗面台に立つとお分かりかと思いますが、鏡像は実体と異なります。見たそのままではありません。その認識がどれほどの精度であるかということになります。特に最低限度となりとも機能を回復することを目指した保険診療では精度よりもとにかく治療をこなすことを求められてしまうためそのミラーテクニックはある種効率的であるかもしれません。
しかし顕微鏡を用いる意義としては拡大して多くの情報量を得られ、それにより肉眼よりもはるかに優れた治療を行える必要がある、というか使うならそうあるべきだということです。肉眼での処置に劣るなら使うべきではないし、勝るならその時に用いるべきとなります。秋山先生が著書でも学会でもおっしゃっていたのは医科における外科ではいかなる拡大視野でもミラーテクニックは用いられない。直視で行われる。(画面を通してなどはある)歯科ではなぜエラーのリスクがあるミラーを積極的に用いられるのか、ということでした。この言葉は非常に私の心に刺さりました。もちろんミラーテクニックはそれ自体は有益な技術といえますが、肉眼レベルで見える範囲の視野ではいいとして顕微鏡レベルの拡大視野では肉眼感覚で手を動かすとかなり大きく動いてしまいます。直視でさえかなり神経を使わないと細かくは動かせないのにさらにミラーテクニックでその細かく動かせるのかということです。
今回のコースではミラーで細かいことを行うことの難しさを身を持って知るセミナーとなり、直視の重要性を理解できることになりました。根管治療においてはラバーダム防湿下の処置においてはミラーテクニックを用いる有用性が非常に高いが、先生によるとそれでも直視の方法があるそうです。今後も学ぶ機会に恵まれればと思います。