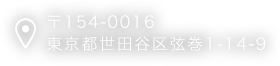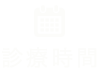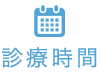矯正治療に関して
副院長の斉藤祐紀です。
私はGP(一般歯科医)ですがこの度歯科矯正を深く学ぶこととしました。というのは日々の診療で自分自身が症例を進める中、矯正で歯を動かすことができたら歯をたくさん削ったり、インプラントを多用せずに成立する症例が意外とあるのではないかと感じたからです。勉強会などに多数参加するとハイレベルな先生は補綴と矯正の利点を充分に活かし融合させて長期予後を確立しています。
補綴(被せ物やインプラント)は補綴の利点があります。それは歯の形を自由に変えることができることです。すり減り、欠けるなどが生じた際、歯自体は復元はしませんが、被せることにより形の復元、またはより理想的な形を作ることが可能です。歯の位置を変えようとすると小さい範囲では可能ですが、あまり大きくすると予後は悪くなる傾向にあります。
一方矯正は歯の位置を変えることができます。補綴では不可能なダイナミックな移動が可能です。(それでも限界はありますが)しかし移動はできますがもちろん形を変えることはできません。
矯正専門の先生は補綴についてはあまり関与できないため、歯の欠損がある矯正のケースを苦手とする場合が多々あります。そのため歯の欠損がありかつ歯並びに問題のあるケースではGPが矯正をできる必要がるか、矯正専門医が一般歯科的な手技を学んで行うかになってきます。
上記の
形を変える
位置を変える
のそれぞれをうまく用いることで理想的な口腔内を仕上げることができます。

まず歯科疾患を持つ患者さんを拝見したら、その症状を治すことはもちろんですが、ゴールをどのように設定するかです。簡単に表現すれば、「ちゃんと咬めてその状態ができる限り長く続く」形にすることがゴールかと思います。そこをきちんと理解するために本多先生のセミナーに参加しました。どういったゴールを目指せば良いか、いわば世界地図を手に出来た勉強となりました。
https://www.saito-dentaloffice.com/blog/咬合・補綴治療計画セミナー第一回を受けて/
https://www.saito-dentaloffice.com/blog/咬合・補綴治療計画セミナー第二回を受けて/
https://www.saito-dentaloffice.com/blog/「咬合・補綴治療計画セミナー」の第三回目を受/
https://www.saito-dentaloffice.com/blog/「咬合・補綴治療計画セミナー」の第4回目を受け/
上記、そのブログになりますので参照いただければと思います。
次にゴールが見えてくるとどのような方法でそのゴールに到達するかということになります。それがより良い治療のためにはさまざまな治療法、高度な技術が必要になります。本来であればこのゴールが見えているからこそどの治療法や技術が必要かを考えることができます。治療法や技術はいわば移動するための乗り物です。陸をできる限り早く移動するのが良いか、海を渡る必要があるのか、空を飛べないとどうにもならないのか。それは目的地があり、その場所がわかっていることが前提の話です。
まさに治療とはそういうことです。
具体例を挙げると
噛み合わせに問題がなく、小さい虫歯が一本というケースです。
こちらはその小さい虫歯を削ってコンポジットレジンという高強度プラスティックを充填することになりますが治療時間も短く1回で終わります。
例えるなら家の近くのコンビニへの買い物です。特に地図を広げることもなく、徒歩か自転車、派手にいっても車を用いるかどうかです。
一方で、歯周病で歯が揺れてしまい、元々の位置から大きくずれてしまったり、歯は何本か抜けてしまった。噛み合わせもずれてしまった、といったケースです。
保険外を用いた方法ではこちらはまず、歯周病を治します。そのためには再生療法が必要になるかもしれません。次に本来の理想的な噛み合わせがなんなのかを診断します。それから歯がずれてしまったところは矯正で理想的な位置へ動かし、歯がないところではインプラントを入れます。
保険内ではまず歯周病を治し、現状の噛み合わせで変更可能かどうかにもよりますが、そこからあまりに位置の悪い歯や予後の悪い歯は抜歯してそこから入れ歯を作製します。
これを例えるとギリシャとトルコの間にあるエーゲ海の島々のとあるホテルへ向かうためにはまず世界地図で場所を理解する必要があります。その上で飛行機を使うのか、船を使うのか、陸で移動も伴うなら鉄道、車はたまた歩きとなるかといった具合です。保険診療の水準で考えると、海上は小さめの船、陸上では車といった具合でしょうか。

確かに、まずゴールの位置がわからないとどのような手段を用いるにしてもどこへ向かえば良いかわかりません。それでは治療したのに咬めない、調子が悪いといった具合になってしまいます。
そしてゴールがわかった上でさまざまな治療法の技術を持つと大型の船、飛行機などの操縦が可能で移動に必要な最適な乗り物を選択できます。そのような研鑽を積まないと車や徒歩程度の選択肢しか取れなくなってしまいます。
上記が咬合、治療計画を立てるための知識とそれを持ってさまざまな技術を持つ必要性といえます。
その中で矯正という技術は長期的に安定した口腔を作り上げる上で非常に強い武器となります。
矯正というのは従来、ワイヤーで歯を動かすものです。しかし治療期間は見た目が悪いことから敬遠されるところもありました。一方で特にコロナ禍以降、世間ではマウスピース矯正が流行っています。これは
ワイヤーでなく歯にマウスピースをはめて歯を動かす矯正です。こちらはパッと見ると特に何もしてなく見え、審美性を気にせず歯を動かすことが可能です。しかし一般的にマウスピースを装着するとわかりますが、上下歯で咬み合いません。つまりマウスピースのみではきちんとした咬み合わせを作ることはかなり難しいです。(もちろんまれにマウスピースだけで咬み合わせを作ることができるケースもあります。)これはマウスピース矯正の限界です。大体のところをマウスピースで動かして、細かいところを従来式のワイヤーで動かすといった具合がよりきちんとした仕上がりとなります。
実際、このコロナ禍においては歯科医師も浅い学習で安易にマウスピースを導入し、ワイヤーが扱えないために中途半端に治療を仕上げてしまうトラブルケースも多々あり、問題となっています。これらをきちんと治すには再び矯正をする必要があります。オプションとしてのマウスピースは患者さんからのニーズも非常に多く、有効な治療法といえますが、適応ケースが多く、一番守備範囲が広いのがワイヤーを用いる方法となります。しかしワイヤーを扱うことは修練が必要でここがGP(一般歯科医)が手を出しにくい、矯正専門医の優位性と言えるところです。GP向けの矯正セミナーも多数存在しますが、愚直にワイヤーを曲げることを指導するものは少なく、どうしても困った時の対応ができるのか不安でした。
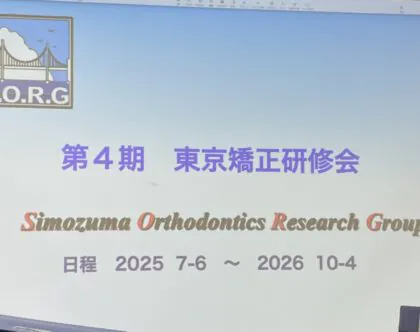
今回受講することとなった下間矯正研修会は40年以上の歴史を持つ業界でも有名な少々スパルタな(笑)矯正セミナーです。それこそまずはワイヤーをきれいに曲げること、それにはまずは手技を知り、あとは自宅でひたすらの練習というように、従来のセミナーというよりも大学の医局のような感じです。これこそが技術力アップの秘訣です。どんなに多くの話を聞いても自分で考え、手を動かすことによる理解には勝らないです。下間先生も大学に居るような症例を見ることは難しいかもしれないが、診断分析や手技は大学の矯正科に数年在籍したレベルに動くようにというのが指導目標とおっしゃっていました。
以上、一年半に及ぶ講習会ですが、しっかりと実力をつけ、通院いただいている患者さん、新たに問い合わせいただく患者さんへ還元できればと思います。